この街には、「景色」が少ない。
長野から東京に越してきて、私が最初に感じたことだ。
これは物語のなかで、地元から上京してきたときに感じることとして、「空がせまい」という表現がたびたび用いられるのに似ている気がする。
「景色なんて、たくさんあるじゃない」
そう言われると難しいのだが、なんとなく整備の行き届いていない木々のある場所や、ビルやマンションのない広々とした土地の風景みたいなものを、私は「景色」と呼んでいる。
「今日は自転車で行こう」

ある晴れた初夏の日、大学時代からの友人から連絡が来て、彼女の家で飲むことになった。
ちょうど休みで暇だった私は、連絡をし終えると、いそいそと準備をしはじめた。
歯を磨いて、髪をとかしている最中、ふと、唐突に思い付いた。
「今日は自転車で行こう」と。
彼女は京成立石駅の近くに住んでいて、いつもはバスで向かっていたのだが、なぜだかこの日は無性に汗をかきたいと思った。
準備もほどほどに、ほぼノーメイクのまま、私は勢いよく自転車を漕ぎだした。
アプリによると、私の住んでいる江戸川区から立石に向かうには、ルートがいくつかあるみたいで、その日はあえて、一番時間のかかる「中川沿いルート」を選んでみた。
バスだと、区役所のある大きい通りに出て、そこから平和橋通りにむかってまっすぐ上っていくのだが、選んだルートとは一つも道が被っていなくて、当たり前だけど、私には行ったことがない場所がまだたくさんあることに気づく。
道のすべてが初めてで、知らないお店や見たこともないお屋敷。はじめましての野良猫。
近所にこんなにあったことが信じられなくて、知らない国に来たような、まるで大冒険をしているような、そんな気持ちになった。
スカイツリーと大きな月

やっと中川沿いに入ると、景色が開けて、まだ夕暮れなのに、黄色くて大きい月がとてもはっきり見えた。
餅つきうさぎも、このときは本当に見えるんじゃないかと思えるくらい、月は近く、大きかった。
空ばかり見ていると、“葛飾区”とかかれた看板を通り過ぎていた。
さらにぐんぐん走っていると、高速道路の向こうから、スカイツリーが顔を出す。
うちの近所でも少し高台に登れば見えることがあるが、中川沿いのスカイツリーはそれよりもはるかに大きくて貫禄があり、シンボルとしてそこに立っていることになんの迷いもないという佇まいをしている。
また少し走ると、いつのまにかさっきの大きすぎる月が、川の向こう岸にあるスカイツリーの横で、陰から見守るように、そっとそこにいるのが目に入り、私は自然に漕ぐのを止めた。

サドルに座ったまま、視線をそらすことができず、しばらくの間、ただただ眺めた。
ひんやりした風で冷やされていく身体にも、くしゃみが出るまで気づかないほどに、私は目の前の景色に見惚れていた。
「私が今日求めていたのは、これを見ることだったのかもしれない。」
そう気づいて、気づいてしまうと余計に感動して、少し涙が出た。
そんな私を横目に、ゆったりとしたスピードで走り抜けていく男性。
よく見ると、ランニングをしている人がちらほら。
私は無性に恥ずかしくなり、慌てて自転車を漕ぎだした。
自転車旅の残りの道中、スカイツリーと大きな月は、私なんか気にも留めていないような気配でそこにいて、なぜだか私は、とても安心した。
恥ずかしくてドキドキしながら、私は考えていた。
自分の家の窓からは、小さくて、ぎゅうぎゅうに建てられた家が立ち並ぶ景色しか見えなくて、私は知らず知らずのうちに、それを窮屈に感じていたのかもしれない。
長野では、いつも山が見えて、家の隣には畑があって、庭には草や花がのびのび生えていた。
その風景が特別恋しいわけではない、自分ではそう思っていたが、知らず知らずのうちに、思い出してしまっていたのだろう。
私は、外にある景色を見に行こうともしないで、無意識に長野で見ていた風景と比べて、悲観してしまっていたのだ。
たしかに長野と比べて、東京は自然の風景が少ない。
けれど、中川沿いで見たスカイツリーと大きな月、あれは私の好きな風景。
東京にもあった。
それは、ちゃんと「景色」だった。
やっと見つけた私の「景色」

その日は無事、友人の家にたどり着くことができ、二人でわいわいお酒を飲んだ。
けれど私にとっては、友人とお酒を飲んだことより、その日見た風景が忘れられなくて、ずっとドキドキしていた。
無干渉に、ただそこにいる「景色」は、私を安心させる。
自転車を止めて、川向うを眺めているとき、ひそかに私は決心していた。
「いましている恋が終わったときは、必ずここに来よう」と。
明確な理由はない。
でもきっと、そんなつらいことが起きたとしても、今日と同じように、あの「景色」は、過度に甘やかすことなく、あの場所でいつも、私をそっと慰めてくれる気がするのだ。
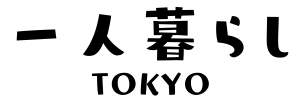









コメント